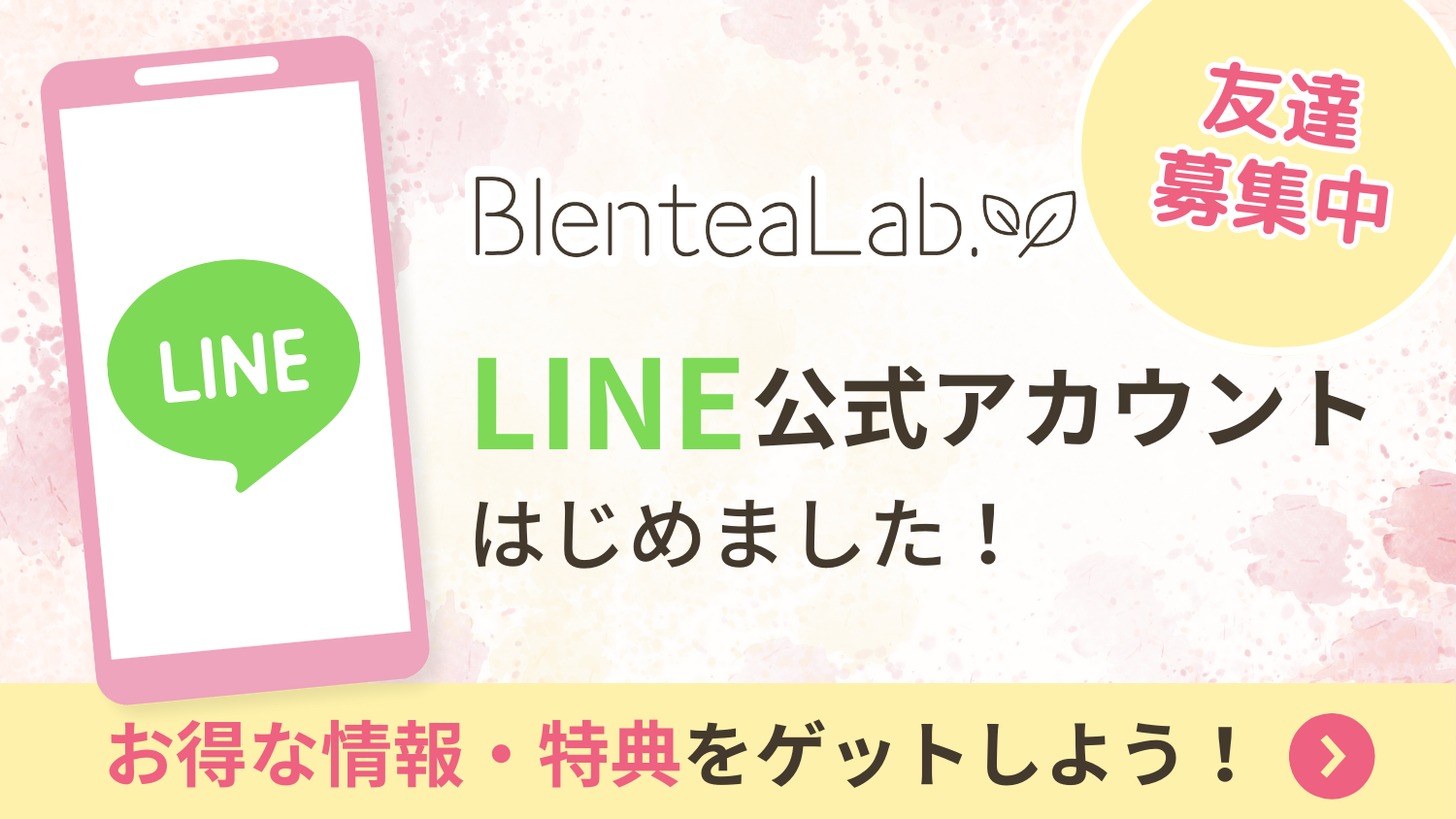カウンセリング茶屋 香逢~KAHOU~
代表 中野邦香
こんにちは♪
薬剤師、国際中医専門員の中野邦香です。
漢方(東洋医学)と予防医学について情報発信している薬剤師です。
日本中にもっと健康的な予防の知識が広まったら嬉しいなぁという思いで日々活動しております。
日々お仕事や子育てにお忙しい毎日と思います。
健康や予防と言ってもなかなかご自身のお身体と向きあう時間も取れませんよね。
そんな忙しいあなたにこそ読んで頂きたい!
体質別に簡単に取り入れられる健康に近づくお話し、そして西洋医学と東洋医学の違いやハーブティーについてお話しさせていただきます!
自己紹介
薬剤師として18年、漢方を勉強し始めて13年が経ちました。
2019年に天津中医薬大学へ1年の研修生として留学して本場の中医学にも触れてきました。
そこから学会発表を経て、様々な方に東洋医学の考え方をお伝えしたいと思い、2023年にカウンセリング茶屋 香逢~KAHOU~を立ち上げました。
なぜ私がここまでに東洋医学を惚れ込んでいるかというと、薬剤師として調剤薬局にて働きはじめた頃、薬局に来る患者様と接している中でふと、病気を予防することができたらもっと幸せに過ごせるのではないか?という思いがわいてきました。
そこから予防医学に興味をもち、アロマテラピーや栄養学や様々なことを勉強していた中でついに東洋医学に出会いました。
東洋医学は予防も治療も両方できる!と思い、勉強を始めました。
その当時27歳だった自分も体調不良で悩んでいました。
生理不順だったのです・・・
婦人科を受診し、ホルモン注射を2回受けましたが生理は来ませんでした。
もう私は生理が来ない身体になってしまったのだ。と本当に落ち込みました。
その時、ちょうど勉強し始めた東洋医学に頼ってみたのです。
当時勤めていた漢方も販売していた調剤薬局の先輩に勧めていただいた漢方を2週間のみました。
すると!たった2週間で生理が来たのです!!本当に嬉しく、そして驚き、この出来事で一気に東洋医学にのめり込むようになり、今に至ります。
西洋医学と東洋医学の違い
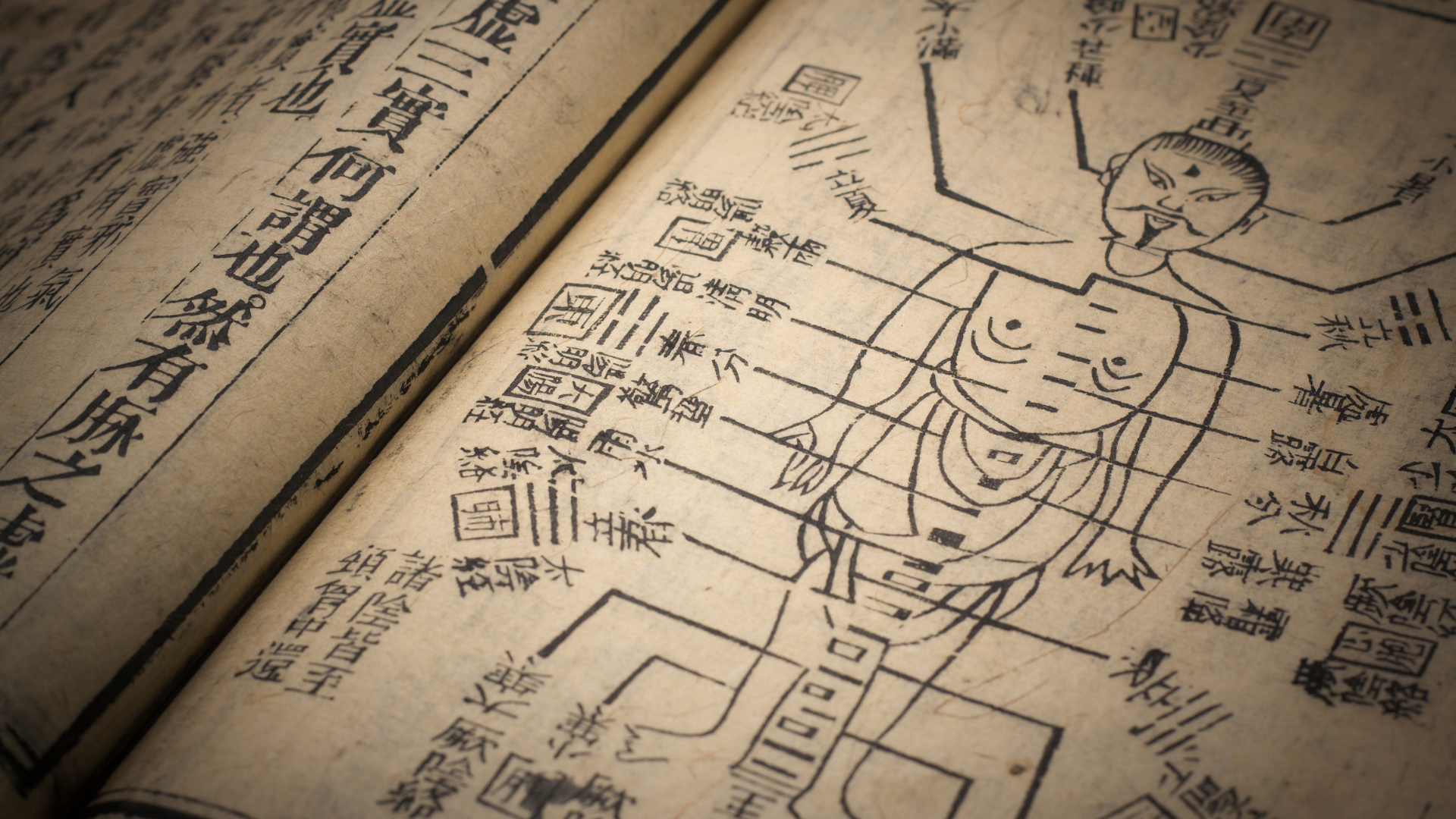
では、内容に入っていきたいと思います。
西洋医学と東洋医学の違いについてです。
皆さんは“東洋医学“と聞くとどのようなイメージをもたれるでしょうか?
なんとなく、気とか見えないものを信じるような少し不思議な世界を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。
私も最初はそのようなイメージをしていました。
ですが、本当にきちんとした理論に基づいた医学なのです。
検査機器などもなく、身体の中を実際に見る事が出来なかった時代から陰陽五行説などに基づいて身体の機能を分類したり、身体の構成成分は気血水だと導いたりしています。
これはのちの西洋医学で言うところの肝臓、心臓、腎臓などの臓器のことや血液、リンパ液に相当する考えです。
では西洋医学と東洋医学の大きな違いとは何でしょうか?
どちらが悪い良いではなく特徴のお話です。
私はどちらも素晴らしい医学だと思っています。
どちらかの医学で不可能なことが、どちらかで可能だと思っているので、皆さんもぜひ西洋医学と東洋医学の違いを理解して頂き、どちらかを選んだり、必要に合わせて同時に取り入れたりして頂きたいです。
西洋医学はそれぞれの専門の科があるように、局部の病気の治療がメインになります。
例えば胃が痛ければ消化器科、骨折や捻挫は整形外科、眠れなかったり気持ちがすぐれなかったりする時は心療内科や精神科などその科その科にそれぞれ受診して部位ごとに検査をして診断されます。
そして治療は基本的にその部位のみにアプローチしていくことが多いです。
対して東洋医学は患者様の身体のバランス全体を考えながら、なぜ今の症状が出ているのかということを総合的にみて治療していきます。
診断方法には
- 問診(症状や体質について質問する)
- 望診(顔や体形や舌の状態などを拝見する)
- 切診(脈診など身体に触れる)
- 聞診(息づかい、声の大小、口臭などを観察する)
の4つの診断方法を活用することで診断します。
治療はその方の元々の体質に重きを置いて、体全体のバランスや季節との兼ね合いなどを考慮して一人一人にあったオーダーメイドの治療をします。
東洋医学的な体質別の健康管理について

東洋医学的に体質や症状から分類した、その体質ごとにおすすめの食材など健康管理についてご説明させていただきます。
東洋医学では体質や症状を分類するには様々な方法があります。
ここでは、身体の中の栄養分(気血水など)から分析する方法をお話させていただきます。
8種類に今回分けて記載しています。
基本的には体質は複雑なので、1つのタイプで体質を分類するよりいくつかのタイプが重なっている場合がほとんどです。
ですので、気になる症状の多いタイプの食材やハーブティーを組み合わせて取り入れてみてください!
皆さんはどのタイプの症状が多く当てはまりますか?
~タイプA:気虚(ききょ)~
主な症状
- 気力がわかない。
- 疲れやすい。
- だるい、少しうごくだけで疲れる。
- 風邪をひきやすい。
- 食欲がない。
- 胃がもたれやすい。消
- 化が良くない。
- 食後に眠い。
- 声が小さい、話すのがおっくう。
- 動くと症状が悪化し、少し休むと改善する。
- めまいやたちくらみ。
- 日中に汗をよくかく。
- 下痢することがある。
- 顔色は白色または黄色っぽい。
- 舌の色は薄く腫れぼったい、両脇に歯形がつく。
おすすめの食材:お米、さつまいも、じゃがいも、やまいも、納豆などの大豆製品、キノコ類、かぼちゃ、鶏肉、豚肉、牛肉、なつめなど
~タイプB:気滞(きたい)~
主な症状
- ゆううつで不安。
- イライラする。
- ちょっとしたことで怒りっぽい。
- 胸部が張って苦しい。
- 喉がひっかかる。
- ゲップがでる。
- しゃっくりがでる。
- お腹が張る。
- 便秘と下痢を繰り返す。
- 食欲が不安定、ため息をつきやすい。
おすすめの食材:シソ、玉ねぎ、みょうが、ピーマン、柑橘類、ジャスミン茶、セロリ、春菊、パセリなど
~タイプC:血虚(けっきょ)~
主な症状
- 動悸、めまい、たちくらみ、目のかすみ。
- 睡眠が浅い、夢をよく見る。
- 顔色が青白い。
- 舌の色が白っぽく、苔が薄い。
- 肌がカサカサ、髪がパサパサで色つやがない。
- 爪や唇の色が薄い。
- 抜け毛が多い。
- ちょっとしたことで不安になる。
- 手足がしびれる。
おすすめの食材:卵、ほうれん草、小松菜、にんじん、黒米、黒豆、黒ゴマ、レーズン、プルーン、豚肉、牛肉、かつお、まぐろなど
おすすめのハーブ:明日葉、くこの実など
~タイプD:瘀血(おけつ)~
主な症状
- 首や肩がこりやすい。
- 頭痛。
- 体の特定の場所が刺されるように痛くて、特に夜悪化する。
- 慢性的な関節痛。
- シミ、そばかすが気になる。
- 唇や爪の色が紫色で暗い。
- 顔色が黒ずむ。
- 眼の周りにクマがきになる。
- 手足の冷え。
- 便が黒っぽい。
おすすめの食材:らっきょう、玉ねぎ、にんにく、ナス、黒酢、黒きくらげ、黒豆、アジやイワシなどの青魚、桃など
~タイプE:陰虚(いんきょ)~
主な症状
- 肌、目ポップタイピング、唇、口の中が乾燥。
- 眼が充血。
- やせ型。耳鳴り。
- 手足や顔のほてり。
- 寝汗をかく。
- 便が固くて、乾燥している。
- 舌が乾燥していて赤みをおびている。
- 短気でイライラしやすい。
おすすめの食材:豚肉、梨、山芋、さつまいも、豆腐、れんこん、大根、はくさい、トマト、エリンギ、もも、黒米など
おすすめのハーブ:くこの実、マリーゴールドなど
~タイプF:陽虚(ようきょ)~
主な症状
- 寒がりで温かいものを好む。
- 低体温ぎみ。
- 尿の回数が多く、尿の色は透明。
(体質により息切れ、胸の辺りが苦しい、水様便、下痢する、足腰が冷たいなど)
おすすめの食材:ニラ、エビ、くるみ、にんにく、長ネギ、シソなど
~タイプG:痰湿(たんしつ)~
主な症状
- 吹き出物ができやすい。
- 頭が重い。
- 身体が重だるい。
- むくむ。
- 吐き気やめまい。
- 痰が多い。
- おりものが多い。
- 舌の苔はべとべとして白い厚い苔。
おすすめの食材:もやし、昆布やわかめやのりやもずくなどの海藻類、こんにゃく、アーモンド、にんじん、はとむぎなど
~タイプH:湿熱(しつねつ)~
主な症状
- むくみやすい。
- 身体と頭が重だるい。
- 尿の出が悪い。
- お通じもスッキリと出ない。
- 舌は黄色の苔がベタベタ、ネバネバしている。
- 炎症している吹き出物が多い。
おすすめの食材:ゴボウ、きゅうり、すいか、大根、黒豆、あずき、はとむぎ、こんにゃく、トウモロコシなど
ブレンドティーをお勧めする理由

東洋医学的な体質管理についてのお話をしてきましたが、その体質にあったハーブやスパイスをブレンドして選ぶことで、東洋医学の視点から心身のバランスを整える効果が期待できます。
気軽に始められる体質ケアとしておすすめです!
自然の恵みを活かした飲み物として、ハーブティーはさまざまな効果が期待できるだけでなく、味や香りのバリエーションも豊富です。
ここでは、ハーブティーをおすすめする理由について詳しくご紹介します。
1. リラックス効果で心を穏やかに
ハーブティーはその香りと成分によって、リラックス効果をもたらしてくれます。
特に、ラベンダーやカモミールは緊張を和らげ、心を落ち着ける効果があることで知られています。
仕事や家事で疲れた夜、ベッドに入る前に一杯のハーブティーを飲むことで、質の高い睡眠をサポートします。
2. 美容と健康をサポート
ハーブティーには、抗酸化作用やデトックス効果が期待できる成分が豊富に含まれています。
例えば、ローズヒップティーにはビタミンCがたっぷり含まれており、美肌効果や免疫力アップが期待できます。
また、ペパーミントティーは消化を助ける働きがあり、胃の不調を和らげるとされています。
日々の健康維持や美容のためにも、ハーブティーは頼れる存在です。
3. 豊富なフレーバーで飽きない楽しさ
ハーブティーは、その種類の豊富さも魅力の一つです。
フルーティーな味わいのものから、爽やかなもの、甘い香りが楽しめるものまで、気分や目的に合わせて選ぶ楽しさがあります。
ブレンドティーなら、オリジナルの組み合わせを試してみるのもおすすめです。
4. 簡単で手軽な贅沢体験
ハーブティーはティーバッグやリーフ状で販売されており、お湯を注ぐだけで簡単に作れるのも魅力です。
お気に入りのカップに注ぎ、好きな音楽を聴きながらの一杯は、日常にちょっとした贅沢をプラスしてくれます。
今までになかった⁈自分好みのお茶を作れる!

「自分だけのハーブティーを作りたい!」と思ったことはありませんか?
そんな夢を叶えてくれるのが、こちらのサイト!
ありそうでなかった新しく、そしてわくわくするサービスです!
自分好みの味をしかも自分でブレンドできます。
ハマる方続出! あなたもきっとこの魅力のとりこに!
BlenteaLab.について
BlenteaLab.さんは、体調や好みに合わせたハーブティーを自分自身でオリジナルブレンドできる今までにないサービスです。
50種類以上の原料から、自分だけのカスタムティーをオンラインでぽちぽちしながら簡単に作成可能!
BlenteaLab.さんでブレンディングしようとして悩んだ際はご相談いただけたら、必要に合わせて健康や美容の目的に合わせたアドバイスも提供させていただきます!
素材や品質にこだわり、ナチュラルなハーブやスーパーフードを使用されています。
ぜひ一度自分だけのオリジナルブレンドティーを作って素敵なティータイムをお楽しみください。
自分にあったハーブティーを日々の生活に取り入れてみませんか?
ハーブティーは、単なる飲み物ではなく、心と体を癒す時間を提供してくれる素敵なアイテムです。
また、体質などのお身体を整えることも可能です。
あなたも忙しい毎日にホッと一息つける時間を取り入れてみませんか?
お好みのフレーバーを見つけて、心豊かなひとときをぜひ体験してください!
手軽に始められるハーブティー。
お気に入りを探して、あなたの日常をもっと豊かにしてみてはいかがでしょうか?
最後に・・・
漢方や美容・健康などより詳しく知りたい方や相談・アドバイスが必要な方はぜひ“こちらのリンク”からインスタグラムのDMにてご連絡くださいませ。
最後までお読みいただきありがとうございます。
こちらの記事もおすすめ



LINE公式でオリジナルブレンドティーを見る!