
温めと冷え性の関係とは?
冷え性の種類と特徴(四肢末端型、下半身型、全身型、内臓型)
冷え性にはいくつかのタイプがあり、それぞれ原因や対策が異なります。
主な冷え性の種類は以下の4つです。
- 四肢末端型冷え性:手足の先が特に冷たくなるタイプで、血流の滞りや筋肉量の少なさが原因です。若い女性に多く見られます。
- 下半身型冷え性:腰や足が冷えるタイプで、デスクワークや運動不足が関係しています。骨盤の血流が悪くなることで起こります。
- 全身型冷え性:体全体の温度が低く、基礎代謝の低下や自律神経の乱れが関係しています。慢性的な冷えを感じることが特徴です。
- 内臓型冷え性:お腹や内臓が冷えやすいタイプで、胃腸の不調や消化機能の低下を招くことがあります。冷たい飲み物や食べ物を好む人に多いです。
冷え性のタイプを知ることで、自分に合った温め方を見つけることができます。
体を温めることが冷え性改善につながる理由
体温が低下すると血流が滞り、酸素や栄養が細胞に行き渡りにくくなります。
その結果、疲れやすさや免疫力の低下が起こります。
体を温めることで、次のようなメリットがあります。
- 血流改善:体温が上がると血管が拡張し、手足の先まで血液が届きやすくなります。
- 基礎代謝アップ:温めることでエネルギー消費量が増え、冷えにくい体づくりができます。
- 自律神経の安定:温熱効果により副交感神経が優位になり、リラックスしやすくなります。
冷え性を根本的に改善するには、日常的に体を温める習慣を取り入れることが大切です。
四肢末端型冷え性の原因と温め対策

血流の悪化と末端の冷えの関係
四肢末端型冷え性は、手足の先が特に冷たくなるのが特徴です。
このタイプの冷えは、血流が末端まで十分に届かないことが主な原因とされています。
血流が悪化する理由には、以下のようなものがあります。
- 筋肉量の不足:筋肉は血液を循環させるポンプの役割を果たします。特に女性は男性より筋肉量が少ないため、冷えやすくなります。
- 自律神経の乱れ:ストレスや不規則な生活が原因で交感神経が過剰に働き、血管が収縮しやすくなります。
- 血液循環の低下:長時間の同じ姿勢や運動不足によって、血流が滞りやすくなります。
このタイプの冷えを改善するためには、血流を良くする習慣を取り入れることが大切です。
温めるために効果的な飲み物と食べ物
食事や飲み物によって、体の内側から温めることができます。
特に、以下の食品や飲み物が効果的です。
- 生姜:血管を広げ、血流を促進する作用があります。紅茶やスープに加えると効果的です。
- シナモン:血行を促し、冷え対策に役立つスパイスです。紅茶やルイボスなどのハーブティー、お菓子に取り入れると良いでしょう。
- 根菜類(ごぼう、れんこん、にんじんなど):体を温める働きがあり、食物繊維も豊富です。
- 発酵食品(味噌、納豆、ヨーグルトなど):腸内環境を整えることで、血流改善や基礎代謝向上に役立ちます。
また、冷たい飲み物は体を冷やしやすいため、できるだけ温かい飲み物を選びましょう。
血流を改善する生活習慣
四肢末端型冷え性を改善するためには、日常生活の中で血流を促す習慣を取り入れることが重要です。
- 適度な運動:ウォーキングやストレッチ、軽い筋トレを習慣化することで血流を促進できます。
- 湯船に浸かる:38〜40℃程度のぬるめのお湯にゆっくり浸かることで、血行が改善されます。
- マッサージ:手足を軽くマッサージすることで、血液の巡りを良くし、冷えを和らげることができます。
- 温める衣服を選ぶ:靴下や手袋を活用し、特に寒い季節には保温性の高い素材を選ぶと良いでしょう。
四肢末端型冷え性は、日々の習慣を少し変えるだけで改善が期待できます。

下半身型冷え性を改善する温め習慣
骨盤周りの血行不良が引き起こす冷え
下半身型冷え性は、太ももやふくらはぎ、足先などの下半身が冷えやすいのが特徴です。
特に女性に多く、デスクワークや運動不足が原因となることが少なくありません。
この冷え性の主な原因は、骨盤周りの血行不良です。
骨盤内には多くの血管が集まっており、ここで血流が滞ると下半身へ十分な血液が届かなくなります。
その結果、次のような症状が現れることがあります。
- 下半身が常に冷たい
- むくみやすい
- 下半身だけ太りやすい
- 生理痛やPMSがひどい
また、骨盤のゆがみや長時間の座り姿勢も、血流を悪化させる要因となります。
下半身を温めるための方法(運動・ストレッチ・入浴)
下半身型冷え性を改善するためには、血流を促進し、下半身を温める習慣を取り入れることが重要です。
1. 適度な運動とストレッチ
デスクワークが多い人は、1時間に1回は立ち上がって軽くストレッチをしましょう。
特に、以下の運動が効果的です。
- スクワット:下半身の筋肉を鍛え、血流を促進する
- 開脚ストレッチ:骨盤周りの血流を改善し、冷えを防ぐ
- つま先立ち運動:ふくらはぎのポンプ作用を高め、血液を循環させる
2. 入浴で体を芯から温める
シャワーだけで済ませず、できるだけ湯船に浸かる習慣をつけましょう。
特に、40℃以下のぬるめのお湯に10~15分浸かることで、血流が改善され、下半身の冷えが和らぎます。
また、入浴時にエプソムソルトや生姜湯を加えると、さらに体が温まりやすくなります。
効果的なブレンドティーや飲み物
下半身型冷え性を改善するためには、飲み物の選び方も重要です。
特に、血流を良くし、体を温める効果のあるハーブティーやスパイスティーがおすすめです。
冷たい飲み物は体を冷やしてしまうため、できるだけ温かい飲み物を選ぶことが大切です。
全身型冷え性を和らげる温め方法
低体温と自律神経の関係
全身型冷え性は、体全体の温度が低く、慢性的な冷えを感じるのが特徴です。
特に、平熱が36℃以下の「低体温」の人に多く見られます。
この状態が続くと、免疫力の低下や疲れやすさ、肩こり、不眠などの症状が現れることがあります。
全身型冷え性の主な原因の一つが、自律神経の乱れです。
自律神経は、体温調整を担っており、交感神経と副交感神経のバランスが崩れると、血流が滞り、体が冷えやすくなります。
以下のような生活習慣が、自律神経の乱れを引き起こす原因になります。
- ストレスの多い生活:緊張状態が続くと、血管が収縮し血流が悪化する
- 不規則な食生活:朝食を抜いたり、栄養バランスが偏ると代謝が低下する
- 運動不足:筋肉量が減少し、熱を生み出しにくくなる
全身を温めるための食生活の工夫
全身型冷え性を改善するには、体を温める食材を意識的に取り入れることが大切です。特に、「陽性食品(東洋医学の考え方に基づいて、体を温める食材のこと)」と呼ばれる食材を摂ることで、血流を促進し、冷えを和らげることができます。
温め効果のある食品
- 生姜・にんにく・ネギ:血行を促進し、体を温める
- 根菜類(ごぼう・れんこん・にんじん):消化がゆっくりで、体を冷やしにくい
- 発酵食品(味噌・納豆・キムチ):腸内環境を整え、代謝を促進
- たんぱく質(鶏肉・魚・卵):筋肉をつくり、熱を生み出しやすくする
また、白砂糖や小麦製品、カフェインの摂りすぎは体を冷やす原因となるため、控えめにするとよいでしょう。
体を芯から温める習慣とブレンドティー
食生活の改善とともに、日常的に体を温める習慣を取り入れることが重要です。
体を温める習慣
- 朝一杯の白湯を飲む:寝ている間に冷えた体を温め、代謝を促す
- 深呼吸を意識する:副交感神経を活性化し、血流を改善
- 軽い運動を習慣化する:ヨガやストレッチで血行を良くする
- 入浴を活用する:シャワーではなく湯船に浸かり、体を芯から温める
おすすめのブレンドティー
体を芯から温めるためには、温め作用のあるハーブティーを取り入れるのも効果的です。
これらのブレンドティーは、日常的に取り入れることで、冷えにくい体づくりに役立ちます。

内臓型冷え性に効果的な温めケア
内臓の冷えが不調を引き起こす仕組み
内臓型冷え性は、お腹や内臓が冷えてしまうことで、全身の不調を引き起こす冷え性の一種です。
手足の冷えとは異なり、自覚しにくいのが特徴ですが、次のような症状が現れることがあります。
- 胃腸の不調(便秘・下痢・胃もたれ)
- 基礎代謝の低下(太りやすい・疲れやすい)
- 免疫力の低下(風邪をひきやすい・アレルギー症状の悪化)
この冷え性の主な原因は、内臓への血流不足です。
血流が滞ると、消化器官や腸の働きが鈍くなり、代謝が低下します。
また、冷たい飲み物や食べ物を摂りすぎると、胃腸の温度が下がり、さらに冷えが悪化することがあります。
内臓を温める飲み物と食べ物
内臓型冷え性を改善するには、食生活の見直しが欠かせません。
特に、体を内側から温める食材を取り入れることで、冷えにくい体をつくることができます。
内臓を温める食材
- 生姜・シナモン:血行を促進し、胃腸を温める
- 味噌・納豆・キムチ:腸内環境を整え、消化機能を向上させる
- 根菜類(にんじん・ごぼう・れんこん):体を温め、腸の働きをサポートする
- 発酵食品(ヨーグルト・チーズ):腸内の善玉菌を増やし、代謝を促す
冷たい飲み物や食品は内臓を冷やすため、できるだけ温かいものを選ぶことが大切です。
温活習慣で内臓を温める方法
内臓の冷えを防ぐためには、日常的に温める習慣を取り入れることが効果的です。
1. 白湯を飲む習慣をつける
朝起きたらコップ1杯の白湯を飲むことで、胃腸を温め、代謝を促進できます。
特に、生姜やシナモンを加えると、さらに温め効果が高まります。
2. 腹巻やカイロを活用する
お腹周りを温めることで、内臓の冷えを防ぎます。特に、へそ下にカイロを貼ると、腸の働きが良くなり、冷えの改善につながります。
3. 入浴で体の芯から温める
38~40℃のぬるめのお湯に浸かることで、血流が促進され、内臓も温まりやすくなります。さらに、炭酸入浴剤や生姜風呂を取り入れると、より効果的です。

温めと不妊の関係|妊活中に意識すべきポイント
体温と妊娠しやすさの関係
妊活中の女性にとって、体を温めることはとても重要です。
なぜなら、冷えによって血流が滞ると、子宮や卵巣の働きが低下し、妊娠しにくい状態になってしまうからです。
健康な女性の基礎体温は、生理周期に伴い変化します。
特に、排卵後の高温期がしっかり続くことが、妊娠しやすい体の目安とされています。
しかし、冷え性の女性は高温期が短かったり、そもそも体温が低かったりすることが多く、受精卵が着床しにくくなる可能性があります。
また、体温が低いと、ホルモンバランスが乱れやすくなります。
エストロゲンやプロゲステロンなどの女性ホルモンは、血流によって運ばれるため、冷えによってホルモンの働きが鈍ることも考えられます。
妊活中におすすめの温め飲み物とハーブティー
妊活中の女性は、体を冷やさない飲み物を選ぶことが大切です。
特に、以下のハーブティーやブレンドティーは、体を温めるだけでなく、ホルモンバランスを整える作用も期待できます。
妊活中におすすめの温め飲み物
- ルイボスティー:抗酸化作用があり、ホルモンバランスを整える
- ジンジャーティー:血流を促進し、子宮を温める
- シナモンティー:代謝を高め、冷えの改善に役立つ
- タンポポコーヒー:カフェインレスで、子宮や腎臓の働きをサポート
これらの飲み物を日常的に取り入れることで、体温を安定させ、妊娠しやすい体づくりができます。
冷え性を改善するためのライフスタイル
冷え性を改善し、妊娠しやすい体を作るためには、日々の生活習慣も大切です。
1. 腹巻やカイロでお腹を温める
特に、下腹部(子宮周り)を温めることが重要です。
お腹を冷やさないために、腹巻やカイロを活用し、常に温かい状態を保ちましょう。
2. 適度な運動を取り入れる
ウォーキングやヨガなどの軽い運動をすることで、血流が改善され、子宮や卵巣の働きが活発になります。
特に、骨盤周りを動かすストレッチが効果的です。
3. 質の良い睡眠を確保する
自律神経のバランスを整えるためには、夜更かしを避け、しっかりと睡眠をとることが大切です。
睡眠中に成長ホルモンが分泌され、ホルモンバランスの改善につながります。

温めに効果的なブレンドティーの選び方
体を温めるハーブとスパイスの特徴
冷え性対策には、体を内側から温めるハーブやスパイスを取り入れることが効果的です。
特に、ハーブティーはノンカフェインのものが多く、妊活中や就寝前でも安心して飲めるため、冷え性の改善に適しています。
体を温める代表的なハーブとスパイスには、次のようなものがあります。
- 生姜(ジンジャー):血行を促進し、体を芯から温める。特に四肢末端型冷え性に効果的。
- シナモン:毛細血管を広げ、血流を改善。甘みがあり、飲みやすいのも特徴。
- ルイボス:抗酸化作用があり、血流を促す。ホルモンバランスの調整にも役立つ。
- カモミール:リラックス効果が高く、副交感神経を優位にすることで血流を改善。
- タンポポ根(ダンデライオンルート):血行を促進し、腸の働きを整える。カフェインレスのコーヒー代替としても人気。
これらのハーブやスパイスや紅茶を組み合わせることで、より効果的に体を温めることができます。
冷えのタイプ別に選ぶおすすめブレンドティー
冷え性にはいくつかのタイプがあり、それぞれに合ったブレンドティーを選ぶことが大切です。
- 四肢末端型冷え性(手足の冷え)
→ ジンジャー+シナモン+ハイビスカス+紅茶
血流を促進し、手足の冷えを和らげる。
ハイビスカスのビタミンCで血管の健康をサポート。 - 下半身型冷え性(腰・足の冷え、むくみ)
→ タンポポ根+ルイボス+黒豆茶
腎臓の働きをサポートし、むくみを改善。利尿作用で余分な水分を排出しながら血流を促進。 - 全身型冷え性(低体温・慢性的な冷え)
→ ルイボスor紅茶+ジンジャー+カモミール
体温を上げる作用とリラックス効果を兼ね備えたブレンド。就寝前にもおすすめ。 - 内臓型冷え性(胃腸の冷え・消化不良)
→ フェンネル+ジンジャー+シナモン
胃腸を温め、消化を助けるハーブを配合。食後に飲むことで内臓を温める効果が期待できる。
おいしく飲むための工夫
ブレンドティーは、飲み方を工夫することでさらにおいしく、効果的に摂取することができます。
- はちみつを加える:甘みをプラスし、喉のケアにもなる。特にジンジャーティーとの相性が良い。
- ミルクや豆乳を入れる:チャイ風(シナモン+カルダモン+ジンジャー+クローブ+ペッパー)にすることで、まろやかで飲みやすくなる。やルイボス、紅茶と相性抜群。
- 長めに蒸らす:スパイスや根っこ系のハーブは、長めに抽出すると有効成分がしっかり溶け出す。
毎日の習慣に取り入れることで、冷え性の改善が期待できます。
まとめ
冷え性には、四肢末端型、下半身型、全身型、内臓型の4つのタイプがあり、それぞれに合った温め対策を行うことが大切です。
体を温めることで血流が改善され、代謝の向上や自律神経の安定、不妊対策にもつながります。
冷え性を改善するためには、適切な食事や飲み物を選び、生活習慣を見直すことが重要です。
特に、生姜やシナモン、ルイボスなどの温め効果のある食材を取り入れたブレンドティーは、無理なく続けやすい温活方法のひとつです。
また、適度な運動や入浴、腹巻の活用など、日常生活の中で体を冷やさない工夫をすることで、より効果的に冷えを防ぐことができます。
毎日の習慣に温活を取り入れ、冷え知らずの健康な体を目指しましょう。
こちらの記事もおすすめ





LINE公式でシングルティー・シングルハーブを購入!
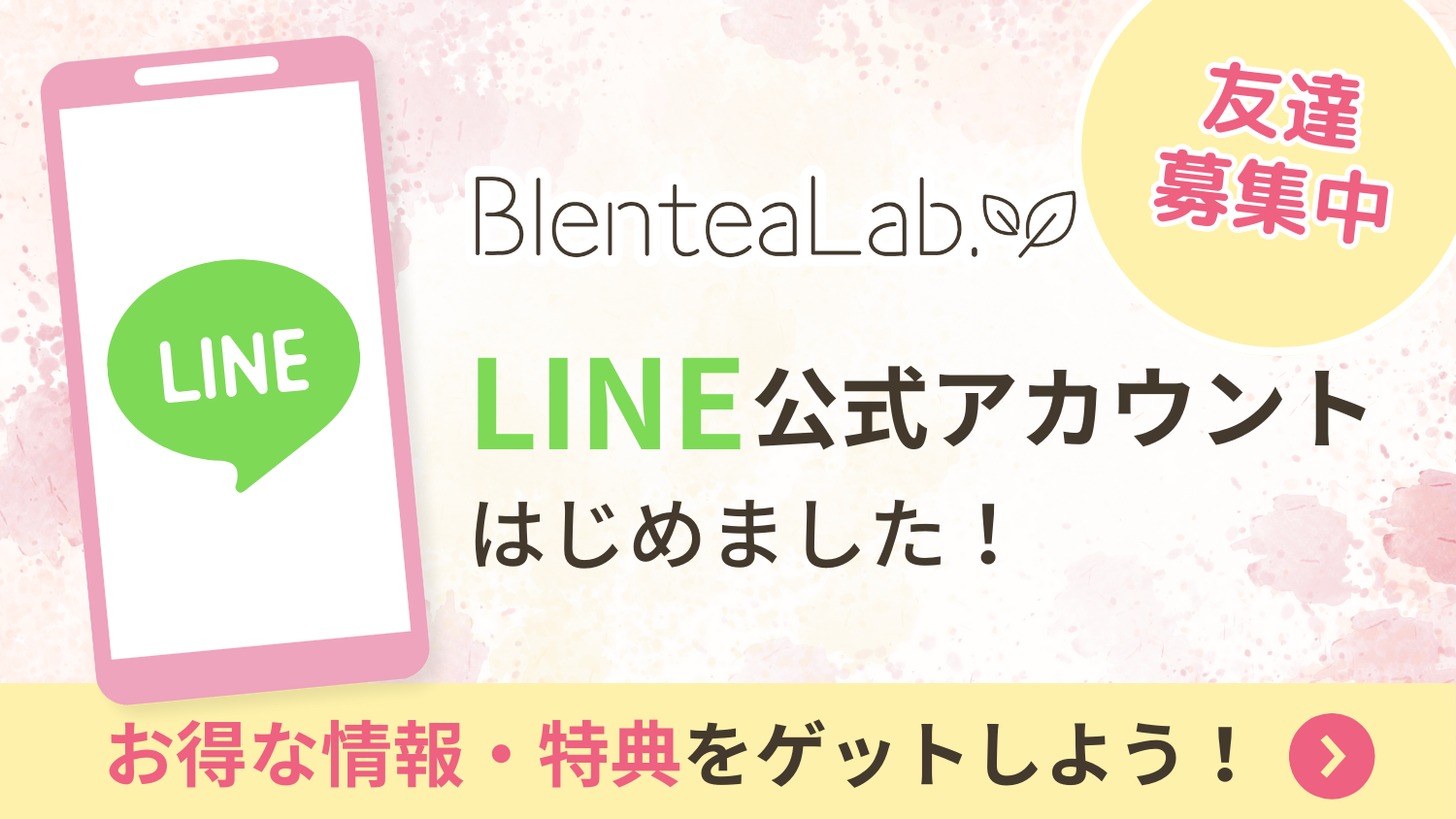
参考文献
厚生労働省 e-ヘルスネット「冷え症」「冷えと自律神経の関係」「冷えと消化機能」「妊活と体温」
日本気象協会「冷え性の種類と対策」
日本生理学会「血流と健康」
日本栄養士会「冷え性対策の食事」
日本整形外科学会「骨盤の健康と血流」
日本薬学会「血行を促進するハーブとスパイス」
日本自律神経学会「自律神経と体温調節」
日本消化器病学会「胃腸と血流の関係」
日本産科婦人科学会「冷えと妊娠の関係」
日本薬学会「スパイスの薬理効果」
